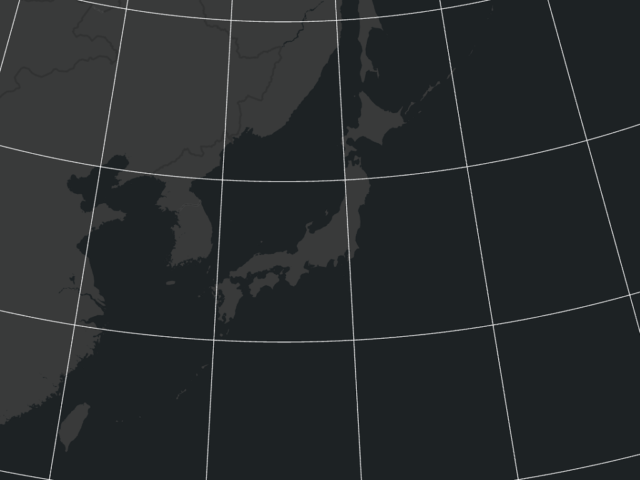基礎知識– category –
-

度分秒と十進度(十進経緯度)の相互換算
地図でよく使われる座標として緯度経度があります。たとえば日本経緯度原点はこのような緯度経度になります。 東経139度44分28.8869秒 北緯35度39分29.1572秒(日本測地系2011) 地理座標は「度(°)」「分(′)」「秒(″)」で表されますが、1度は60分で1分は60秒となり、「度」は十進数で「分」と「秒」は六十進数です。このような異なる... -

ジョンソンの定理
最近は Google Maps などで高解像度の衛星画像が閲覧でき、おおむね普段関わる地物を認識することができるようになりました。しかし、無償でダウンロードできる衛星画像の解像度はまだまだ低いものが多いです。最新のランドサット8号だと分解能 30m(パンクロで 15m)です。 では、どの程度の解像度で地物の認識ができるのでしょうか。低い解... -

日本全国に適用できる最適な正積図法は何か?
「日本全国を表示するのに最適な投影法は何ですか?」 よくある質問です。最近は回答として次の正積図法とパラメーターを使っています。 日本の GIS講習で最初に習う具体的な座標系は地理座標系、UTM座標系、平面直角座標系ぐらいで、投影座標系は割と狭い範囲に適用できるものしか教えられません。世界地図ならメルカトル図法とか学校で習っ... -

縮尺と精度
学生時代、大学の授業で GIS データに縮尺の概念はない。精度が重要である。 と一番に教えられました。 当時は呪文のように GIS データは「縮尺」ではなく「精度」と覚えてきましたが、ここにきて「精度」とは何かを説明しなさいと言われるとあいまいな回答しかできなかったので、あらためて調べてみました。 縮尺 = 地物を模した地図の1辺... -

日本周辺座標系のWKID一覧
日本でよく利用される座標系の適用区域と原点、WKID を示したポスターです。 -

国土地理院の小縮尺地図に使われている地図投影法
はじめに 国土地理院が刊行している地図の投影法について調査する機会があったので掲載します。 よく使う25000分の1地形図などはUTM図法で有名ですが、小縮尺はあまり知られていません。パラメータはなおさらなのでまとめてみました。 国土地理院発行小縮尺地図の投影法 図名図郭名地図投影法標準緯線1標準緯線2中央子午線中心緯度中心経度50... -

位置情報の記述方法
場所を特定する方法、代表的なものは「経緯度」と「住所」で、地理情報標準では前者を「座標による空間参照」、後者を「地理識別子による空間参照」といいます。簡単な呼び方で「直接位置参照」、「間接位置参照」と呼ばれたりもします。 その他の地理識別子として、国が整備している地域メッシュという範囲を示したコードがあります。これは...